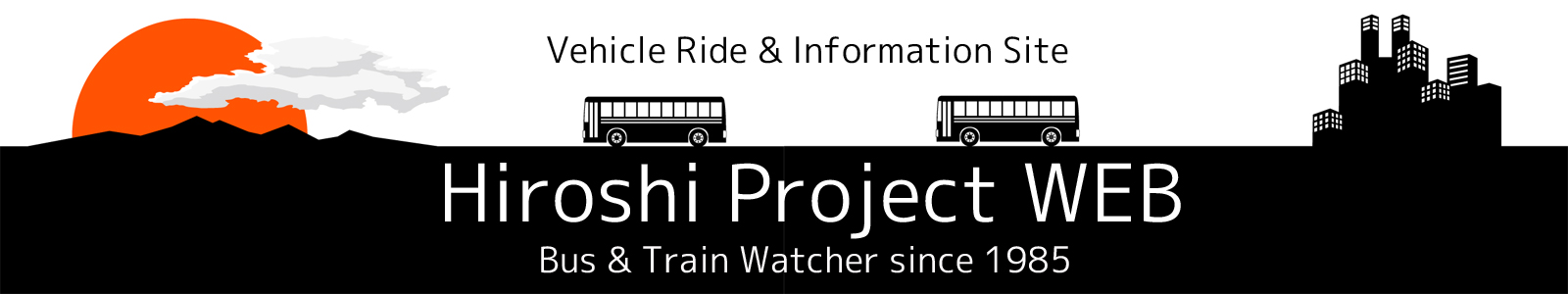気になる西鉄「はかた号」の外観と車内
何度かご紹介していますが、西鉄「はかた号」の現行車両について、改めてご紹介します。
今回乗車した車両はこちら↓。
西日本鉄道博多自動車営業所所属の0001号車(三菱エアロクイーン 2TG-MS06GP)です。
2020年7月1日に運行を開始した最新車両で、パールホワイトメタリックの車体に「Line connecting Hakata with Tokyo」のロゴが入った「はかた号」専用カラーリングの外観は変わりませんが、フロントマスクが2019年モデル(いわゆる「令和顔」)に変更されたことにより、より精悍になった印象を受けます。
車内は、先代の「はかた号」専用車を踏襲した23人乗りの夜行高速仕様。
前方4席が個室タイプの「プレミアムシート」、後方19席(予備席を含む)が3列独立の「ビジネスシート」になっています。
プレミアムシート
最上級シートの「プレミアムシート」は、先代の専用車と同様にマジカルテクニカ製バス用シートを採用しています。
シートスペックは、シート座面幅約56cm、背もたれ幅約69cm、最大リクライニング角度150度、シートピッチ135cmとなっており、先代車両のプレミアムシートと比較すると、座面幅が約6cm、背もたれが約19cm拡大されています。
ゆったりとした座り心地が特長です。
プレミアムシートの詳細については、下記の記事にて紹介していますので、併せてご覧いただけると幸いです。
ビジネスシート
そして、こちらが今回私が乗車した、車内後方に設置されている3列独立タイプの「ビジネスシート」です。
ビジネスシートは、車内後方部に19席(予備席1席を含む)設置されています。
画像はありませんが、全席にフェイスカーテンを設置しており、座席の横のみならず前後も仕切られることから、狭いながらも個室感覚で眠ることが出来ます。
詳しく見ていきましょう。
シート自体は、一般的な夜行用シートをベースにした本革仕様になっています。
但し、背もたれについては、本革とモケットの組み合わせとなっており、モケット部分がシートデザインのちょっとしたアクセントにもなっています。
先代のビジネスシートは、プレミアムシートと同様のマジカルテクニカ製を採用していましたが、今回の新型車両においては、シート形状やスイッチ類を見るに、天龍工業製の特注シートを採用しているものと推測されます。
シートスペックは、シート幅約46cm、最大リクライニング角度約143度、シートピッチ約95cmと、先代のビジネスシートとスペックは変わりませんが、ダブルクッションを採用するなどの改良が施されています。
3点式シートベルトを全席に採用するなど、安全・安心を売りにしているのが特長です。
肘掛下には、シートのリクライニングボタンとSOSボタンを設置しています。
シートのリクライニングは、青色の輪が付いたボタンを押しながら背もたれを押すと、シートが倒れる様になっています。
また、肘掛は先端のボタンを押すと下に倒れる様になっています。
レッグレストと足置き台(フットレスト)です。
足置き台(フットレスト)は、足を伸せる面がモケットになっており、靴を脱いで脚を伸ばした際に滑りにくくなっています。
また、足置き台の奥行きは空洞になっており、脚をゆったりと伸ばすことが出来ます。
シートポケットです。
各種案内リーフレットと使い捨てスリッパが入っています。
読書灯は、前席のシート背面とエアコンダクト(窓側座席のみ)の2箇所に設置。
この点においては、プレミアムシートよりも優れているといえるでしょうか。
肘掛の下には、モバイル充電用のUSBポートが一口設置されています。
プレミアムシートと同様、コンセントタイプではないので注意しましょう。
ビジネスシート利用者に提供されるお茶と使い捨て方式のアイマスクです。
その他の設備
トイレは、車内中央部の階段を下りた突き当たりにあります。
この車両に限ったことではありませんが、あくまで非常用と考えた方が良いかもしれません。
無料Wi-fi「Kyushu Bus Network Free Wi-fi」も完備しています。
1回の接続時間は最大720分です。
細かなところでは、この様な工夫も。
写真は、シートベルトのバックルですが、シートベルト非着用時にバックルのLEDランプが点滅する様になっています。(写真はプレミアムシートのシートバックルです。)
安全対策も強化されています。
この車両には、EDSS(ドライバー異常時対応システム)を搭載。
車内の車両停止スイッチは、プレミアムシート1A/1B席の外壁上部に取り付けられています。(写真はイメージです。)
また、この車両には、左折時の巻き込みを防ぐ機能(アクティブサイドガードアシスト)や、タイヤの異常を検知するTPMS(タイヤプレッシャーマネジメントシステム)を導入。
これらの装置の一部は、通信型ドライブレコーダーと連動しており、運行管理者がリアルタイムで運行の状況を確認することで、万一異常が発生した場合に迅速に対応することが出来る様になっているそうです。
(次ページに続きます。)